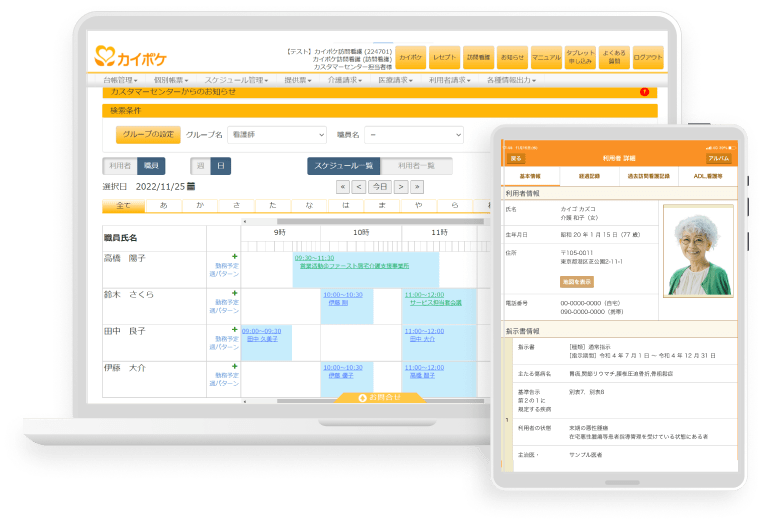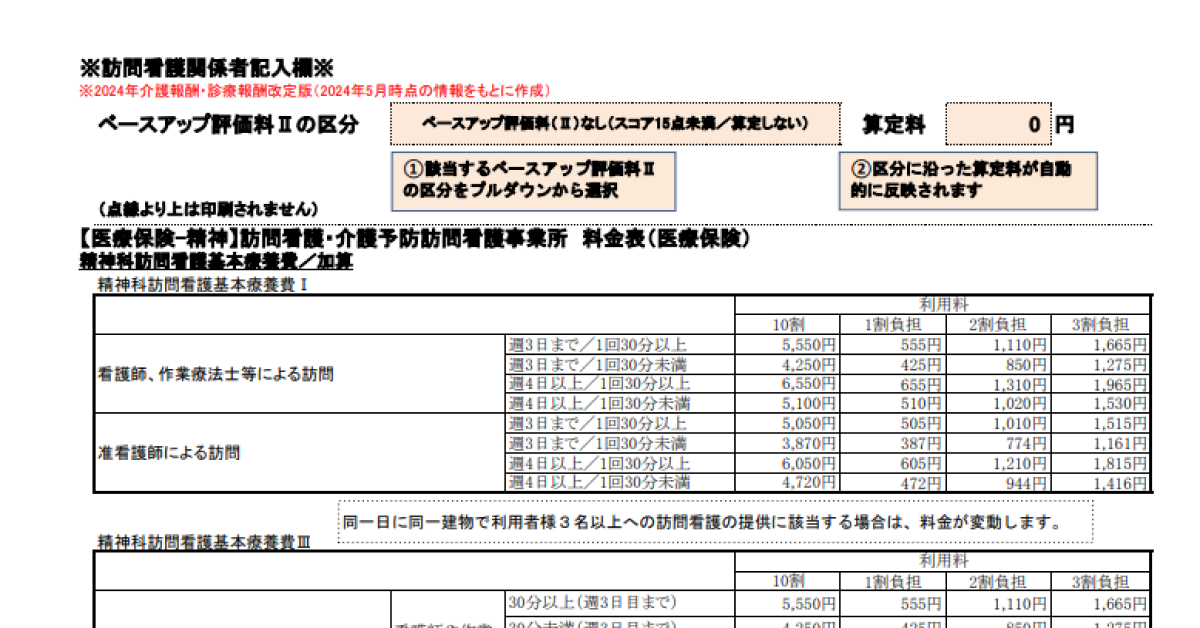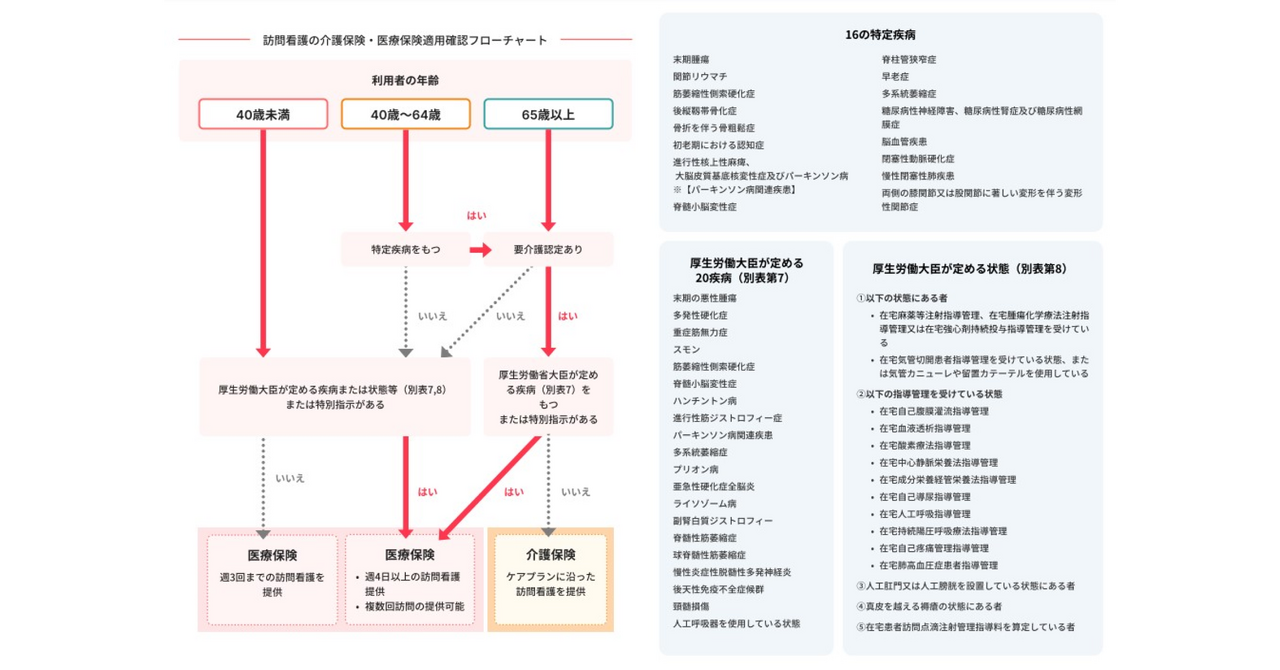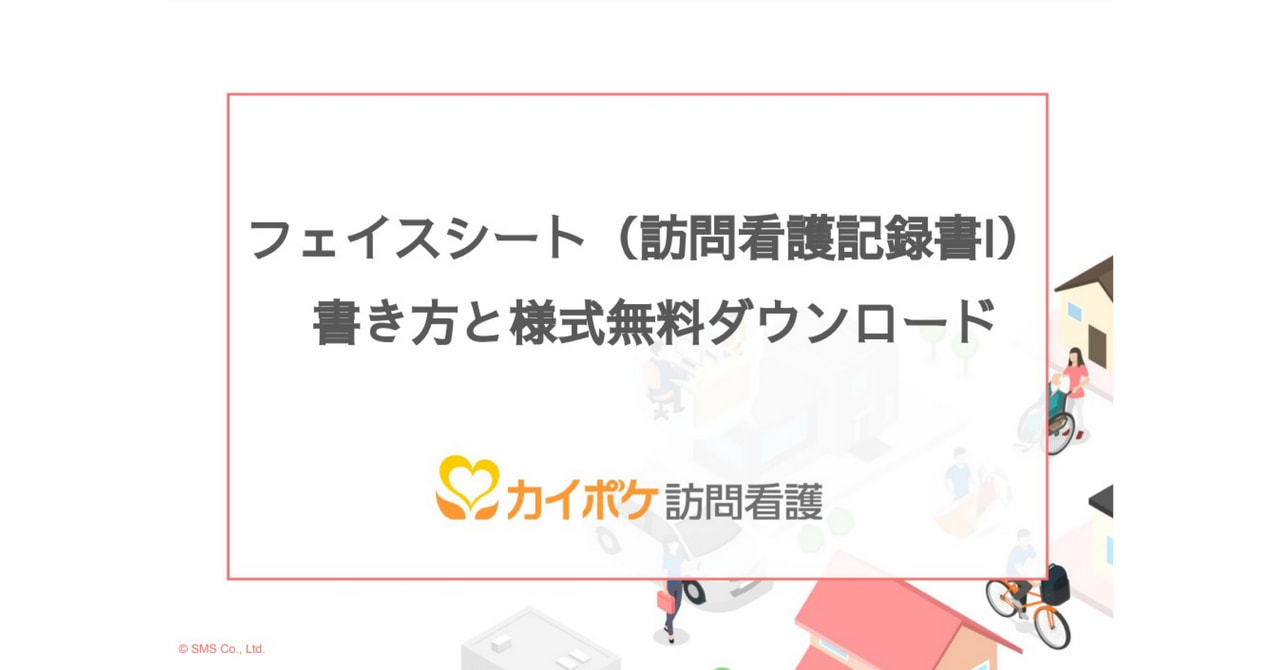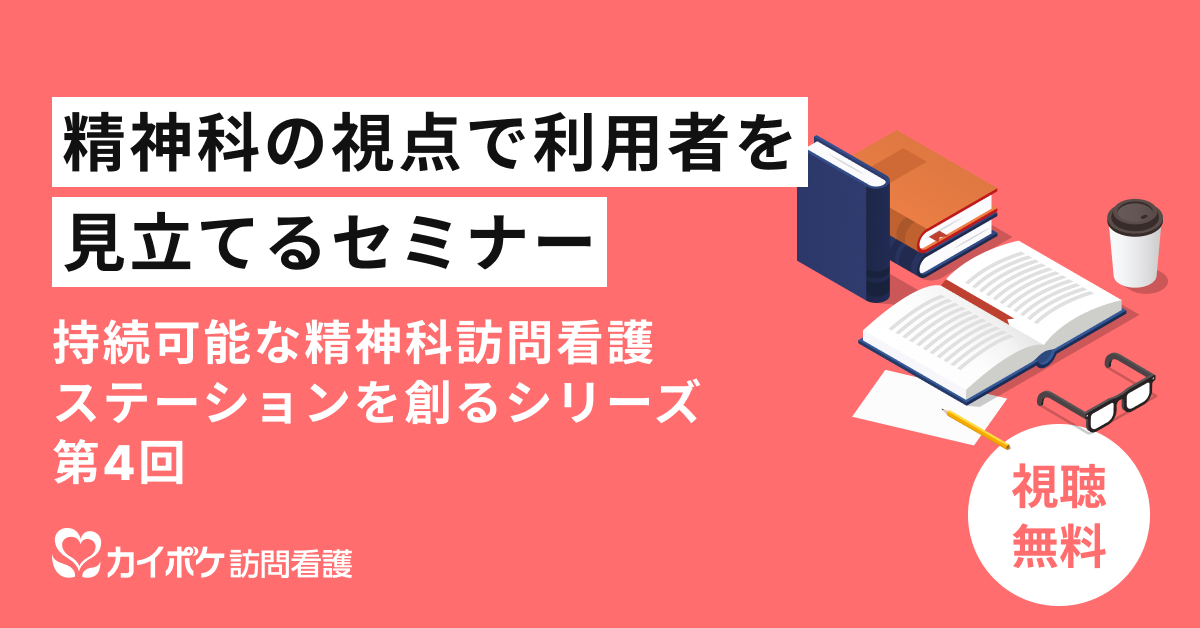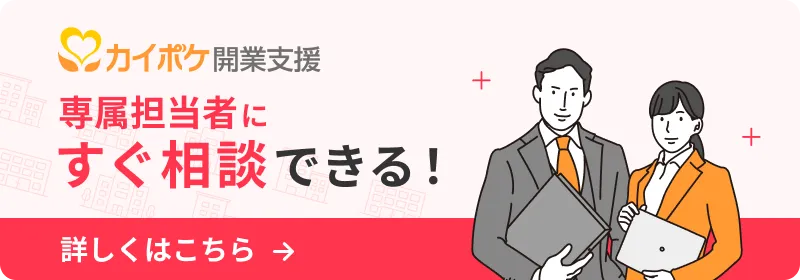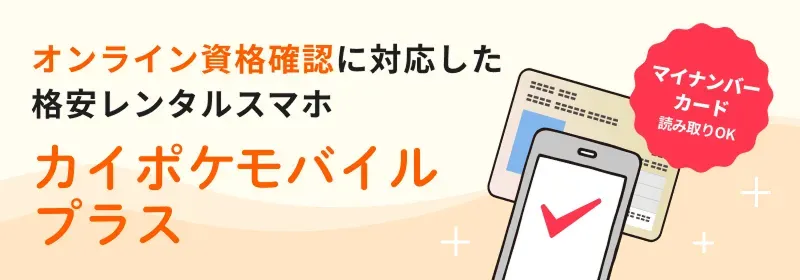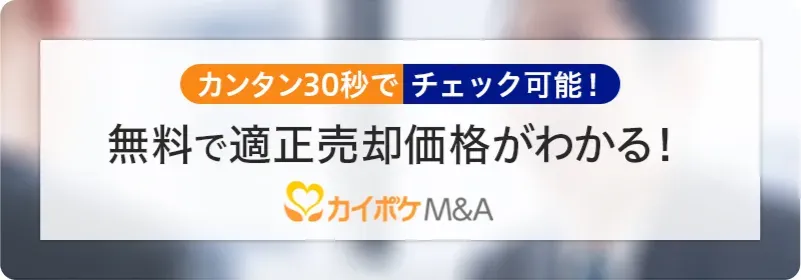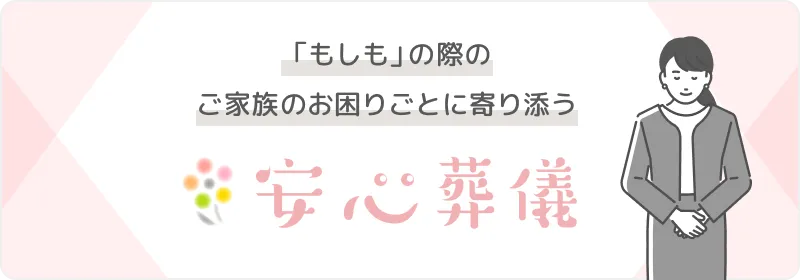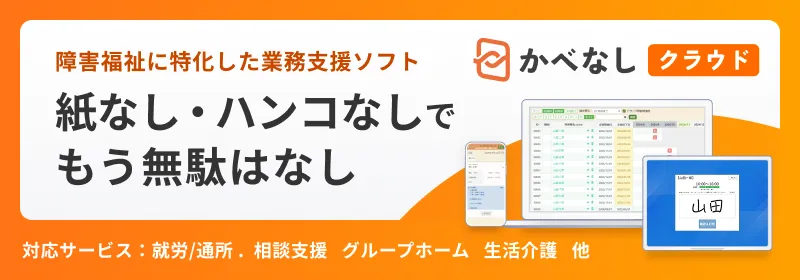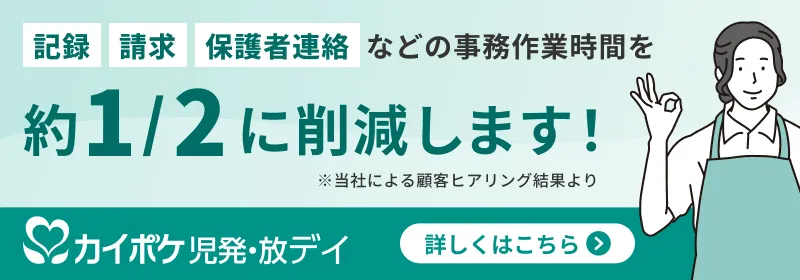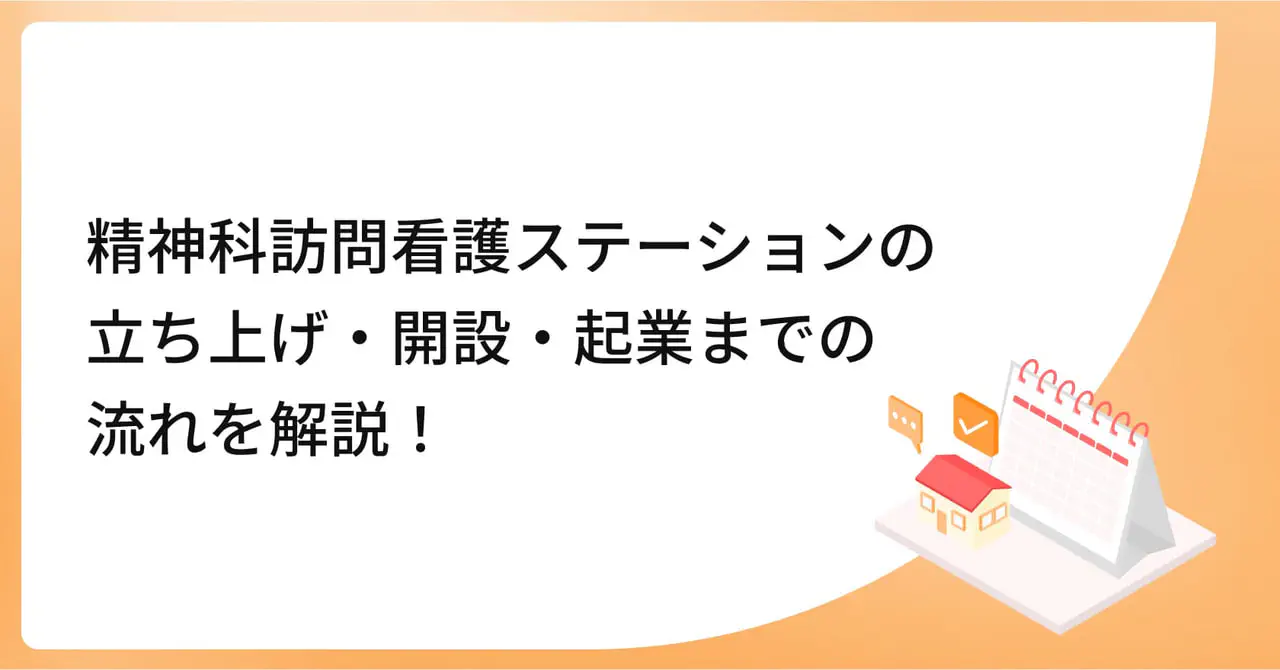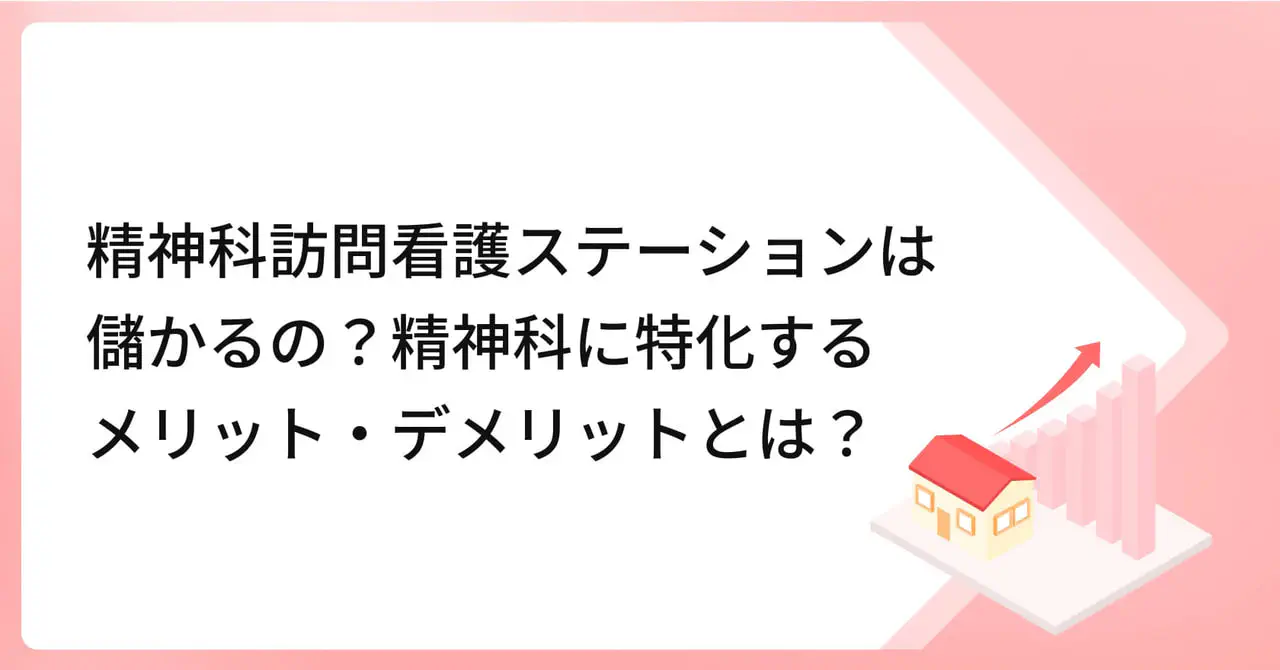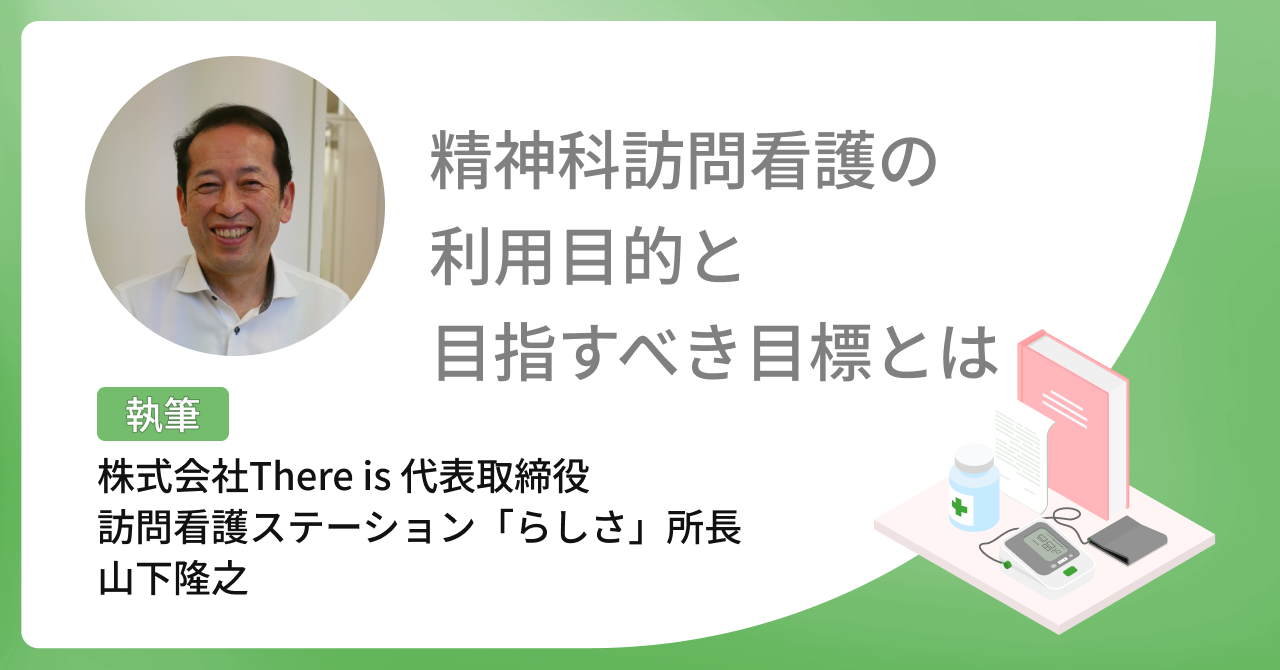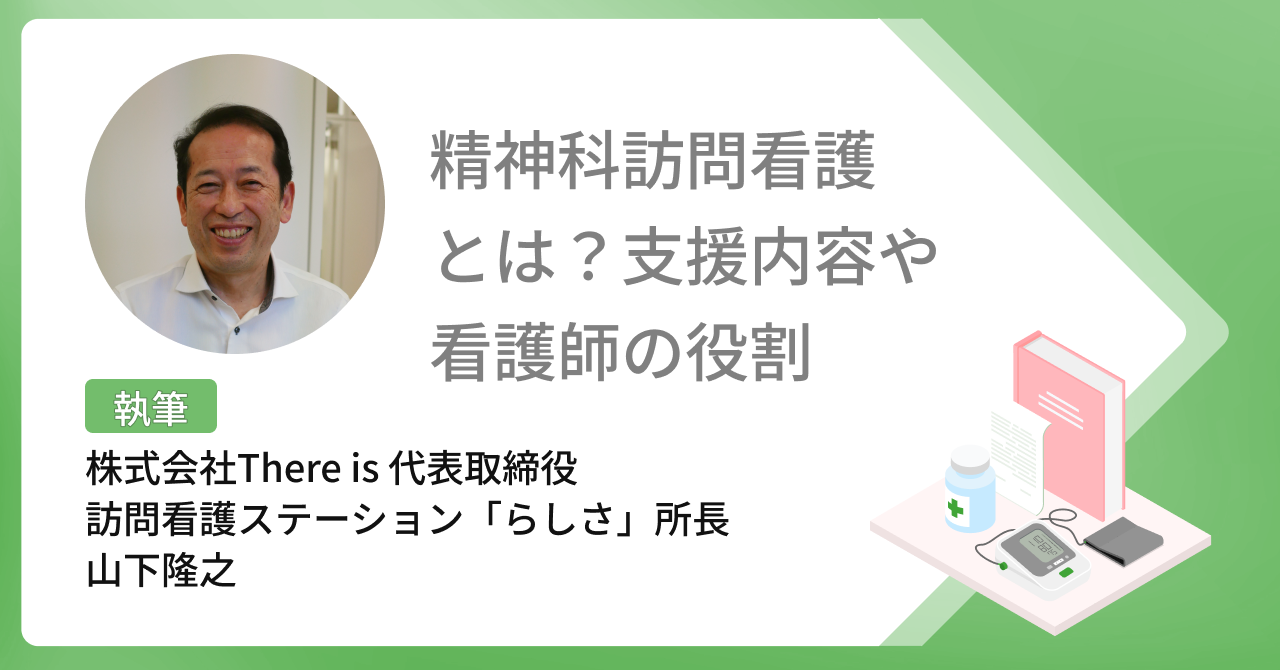キャンセルには理由が存在する ~精神科訪問看護のキャンセル問題にどう取り組むといいのか~
公開日: 更新日:
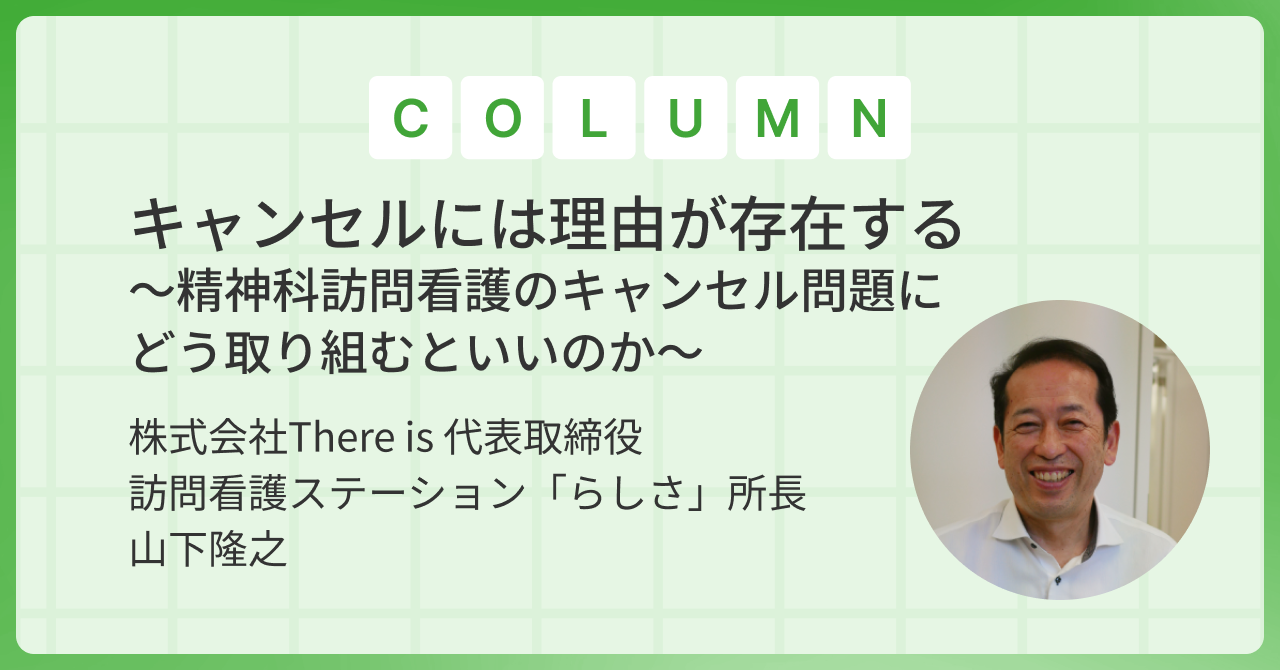

株式会社There is 代表取締役 訪問看護ステーション「らしさ」所長 山下隆之
看護師・精神科認定看護師資格を取得。株式会社There isを設立後、精神科特化の訪問看護ステーションらしさを開設。著書に『精神科仕事術この科で働くことを決めた人がやったほうがいいこと、やらないほうがいいこと』がある。
目次
精神科訪問看護において、利用者さんから予定の訪問をキャンセルされることは少なくありません。
キャンセルが多くなると経営を圧迫することになり、キャンセルを減らすことは事業所の重要なテーマの一つになっているのではないでしょうか。
しかし、実際にキャンセルを減らすことは容易ではありません。利用者さんがキャンセルをする背景には、事業所の対応や訪問看護の内容への不満、個々の利用者さんの状況や考え方、そして利用者さんと訪問看護師の関係性などが複合的に絡み合っていて、こうすればキャンセルが減らせるという明確な答えがないからです。
ここでは、キャンセルを減らすために、利用者さんのキャンセルがある背景をどのように捉え、考え、対応していくといいかについて述べたいと思います。
キャンセル料の規定について考えることからスタート

精神科訪問看護では、利用者さんからキャンセル料を取るか取らないかの規定は、事業所の裁量で決めることができます。
多くの事業所は、当日のキャンセルや無断キャンセルの場合は、キャンセル料が発生するという規定を作っているのではないでしょうか。
しかし、現状では、利用者さんから当日にキャンセルの連絡があっても、利用者さんの状況や経済的負担を考慮して、規定通りに実施していない事業所が多く見受けられます。
私は、規定通りに実施しないことがキャンセルを減らせない一つの要因になっていると考えています。
訪問看護は利用者さんの同意と協力があって成り立つサービスです。契約に当たって、利用者さんには、決めた時間に訪問看護を受ける責任があることを伝えることが必要です。
また、当日のキャンセルはキャンセル料が発生することを説明して同意を得られたら、規定通りに実施することが大切です。双方で約束したことを守ることは、利用者さんへの「ケア」であり、規定通りに実施することで利用者さんは契約上の責任を果たす大切さを学ぶ機会になります。
実際に、当日キャンセルがあった利用者さんから規定通りにキャンセル料を頂いたことで、それ以後、利用者さんのキャンセルが減ったというエピソードがあります。
もし、現状規定通りに実施できていないようであれば、キャンセルの取り扱いについて事業所内でよくよく再考して規定を作り直し、まずはその規定通りに実施していけるとよいと思います。
契約にそって規定通りに実施することは、単にキャンセルを減らすということだけではなく、長い目で見ると事業所への信用につながっていくと私は思います。
キャンセルには理由が存在する

キャンセルをする利用者さんには、キャンセルをする理由があります。それは利用者さんの考え方によって異なりますが、キャンセルをする理由は大きく分けると以下の2点だと私は考えています。
1点目は、利用者さんがそもそも訪問を必要と考えていないケースです。
2点目は、利用者さんが事業所の対応や訪問のあり方に不安や不満を持っているケースです。利用者さんが、この2点を持ったまま利用を続けていると何かが引き金になって突然契約を終了されるということも少なくありません。キャンセルがある利用者さんに対しては、この2点の理由がある背景を踏まえ、個別に対応していくことが必要です。
ここでは、この2点を踏まえ、具体的にどのように考え、対応していくといいのかについて考えたいと思います。
利用者さんが訪問を必要と考えていないケース
利用者さん以外の他者から訪問依頼があったケース
精神科訪問看護の依頼は、当事者自身からよりも、その家族、通院先の主治医、相談窓口の相談員さんなど他者からの依頼が圧倒的に多いです。
そういったケースでは、契約するにあたって、当事者自身が精神科訪問看護を利用する意思があるかどうかの確認が必要不可欠です。
これまで当事者の意思確認をしないまま、家族や主治医の意向を優先に契約をしてしまった結果、当事者は疎外感を感じたり事業所に不信感を抱いたりして、キャンセルが続き、早々に終了してしまうケースが多くありました。
契約するにあたって最も大切なことは、当事者が利用したいかどうかの意思確認をすることだと思います。
頻繁にキャンセルをする利用者さんのケース
利用者さんの中には、所用や体調不良で頻繁にキャンセルをされる方がいます。
そんな時は、まずはキャンセルをする利用者さんの理由や心情を聞き、その気持ちを受けとめることが大切です。その上で、契約した以上は利用者さんにも決められた時間に訪問を受ける責任が伴うことを再度説明して、どうやったらキャンセルしないで済むかを訪問看護の時間を利用して一緒に考えるとよいと思います。
それは関係を築いていくことに課題がある利用者さんにとっては必要な「ケア」であり、そのプロセスそのものが関係性を築いていくプロセスになっており、結果として訪問看護の必要性を感じて継続して訪問を利用してもらえるかもしれません。
また、利用者さんの状況によってキャンセルがあるケースでは、訪問の日時を変更したり、頻度を減らしたりすることでキャンセルが減ることもあります。
利用者さんが不安や不満を持っているケース
自宅に訪問看護師を招き入れることに不安を持っているケース
利用者さんの中には、訪問を利用する前提として、他人を自宅に招き入れることに抵抗感や不安感を持っている方が多くいます。自身の安全なテリトリーに他者が入ってくると誰でも不安になります。
利用者さんの中には他者との物理的距離に敏感な方が多いので、訪問時にはその利用者さんの安心できる物理的距離を取れるとよいと思います。
一般的には人間は手足の届く距離に他者がいると本能的に不安を持つので、少なくとも1メートル以上の物理的距離を取れるとよいと思います。
また、お部屋が乱雑で、申し訳なさから他者を招き入れることに抵抗を感じる方もいます。そんな時は、訪問時にお部屋をきょろきょろ見回したりせずに、普段通りに訪問することが大切です。
世間体を気にされるケース
精神科はまだまだ社会の中で根強い偏見があり、利用者さんの中には世間体を気にして訪問を利用することに躊躇される方もいます。
そのことを前提に契約時は、車をどこに停めたらいいかを聞き、入口のインターフォンでは訪問看護という言葉を使わないでおくなどの説明と配慮があるとよいと思います。
事業所としては訪問看護ステーション名が入っている社用車の使用や訪問看護師の服装などもよく考え、精神科の訪問看護を利用していることが近隣の方などに気づかれないような配慮が必要なケースもあります。
訪問看護のあり方に不満を持っているケース
利用者さんは個々の特性や考え方で訪問看護のあり方に不満を抱き、キャンセルにつながっていることが多くあります。そういったケースでは、不安や不満を察知して対処していくことが必要です。
キャンセルがあった時はその理由を聞き、事業所で対処できることは迅速に対応し、対応できない時は、誠実さを持って伝えることが大切で必要です。
利用者さんによっては不満を伝えることに抵抗を感じる方も多く、不満を伝えられないまま終了してしまうケースも少なくありません。
そういったことがないように苦情窓口があることを事前に説明しておき、不満がある場合にはその不満を教えてほしいと利用者さんにお願いしておくとよいと思います。
不満を教えてもらうことは、事業所がよりよく変わることができるチャンスだとポジティブに捉えられるとよいと思います。
訪問看護師の言動に不安や不満があるケース
キャンセルにつながるケースで最も多いのは、利用者さんが訪問看護師の言動に不安や不満を抱いた時だと思います。
そうならないために、訪問看護師に求められることは人を大切に考える倫理実践です。具体的には敬語を使う、穏やかな態度を維持する、身だしなみを整え、清潔感のある服装を着こなすことなどです。においに敏感な方も多いので柔軟剤などのにおいが強くないかどうかなどにも気をつけるとよいと思います。
利用者さんの個人情報を守ることも大切です。
訪問で得た情報は主治医以外には伝えない、他の連携機関などと情報共有したい時は、利用者さんの同意を得てから伝える配慮も必要です。訪問看護師の言動でキャンセルにならないためには、倫理実践力を高め、利用者さんから信頼を得られるかどうかが鍵だと思います。
事業所においては、倫理実践能力を高められる教育制度が必須です。それで信頼を得られると、キャンセルが減るだけではなく、口コミで利用者が増えることにつながると思います。
期待と違うことに不満を持っているケース
利用者さんは、訪問看護でこうしてほしいという要望を持っています。実際に訪問開始になると要望と違う対応に不満でキャンセルされるケースもあります。
そういったことにならないようにするためには、契約時に利用者さんが訪問看護に期待することを聞いた上で、訪問看護でできることとできないことを明確にして説明し、同意を得ることが必要です。
説明不足で訪問が始まってから要望と違うと感じるとキャンセルが続き、どこかで終了してしまうケースがあります。利用者さんが不満でキャンセルに至らないようにするには、契約時に利用者さんのニーズを把握し、説明、同意、納得した上で契約することが必要です。
実際にキャンセルがあった時はどうしたらいいか
キャンセルがあった時の対応の原則は事業所で決めておくとよいと思います。
一般的には、その理由を聞き、振替で訪問を利用してもらえるかの提案をして、振替が難しければキャンセルを認めて次回の訪問日時の確認をするという流れになります。
しかし、利用者さんそれぞれの状況や考え方があり、キャンセルの連絡があった時は、それぞれの利用者さんの特性に合わせて事業所内で対応方法を共有しておくとよいと思います。
例えば、一度決めたら考えを変えられない利用者さんであれば、振替の提案をしないですぐにキャンセルを認めるケースもあっていいと思います。
また、利用者さんによっては電話をするのが苦手な方も多く、連絡方法についても個別に対応を考え、メールでやりとりをするなど利用者さんの特性に合わせて対応を考えることで継続して訪問を利用してもらえるかもしれません。
まとめ
キャンセルの取り扱いについては、単にキャンセルを減らすことを考える前に、そもそもキャンセルをしないように、利用者さんには決めた日時に訪問を受ける責任があることを伝え、協力依頼をすることが必要です。
その上で、利用者さんそれぞれのキャンセルをする背景を踏まえ、事業所の対応や訪問看護のあり方について考え、倫理実践能力を高めることでキャンセルが減っていくのではないかと思います。
キャンセルを取り扱うプロセスは、利用者さんから信頼を得られるプロセスでもあり、結果として継続的に精神科訪問看護を利用してもらえることになると思います。
便利な資料をダウンロード
電子カルテや医療・介護レセプトなら カイポケ訪問看護
無料のデモ体験や詳しい資料をご覧になりたい方は
こちらからお申し込みください

訪問看護に関する
無料セミナー
開催中
必要な機能がオールインワン