「幸せに働き続ける環境をつくる」ために始まった生成AIの活用
- 電子カルテ
- 業務効率化
- 生成AI


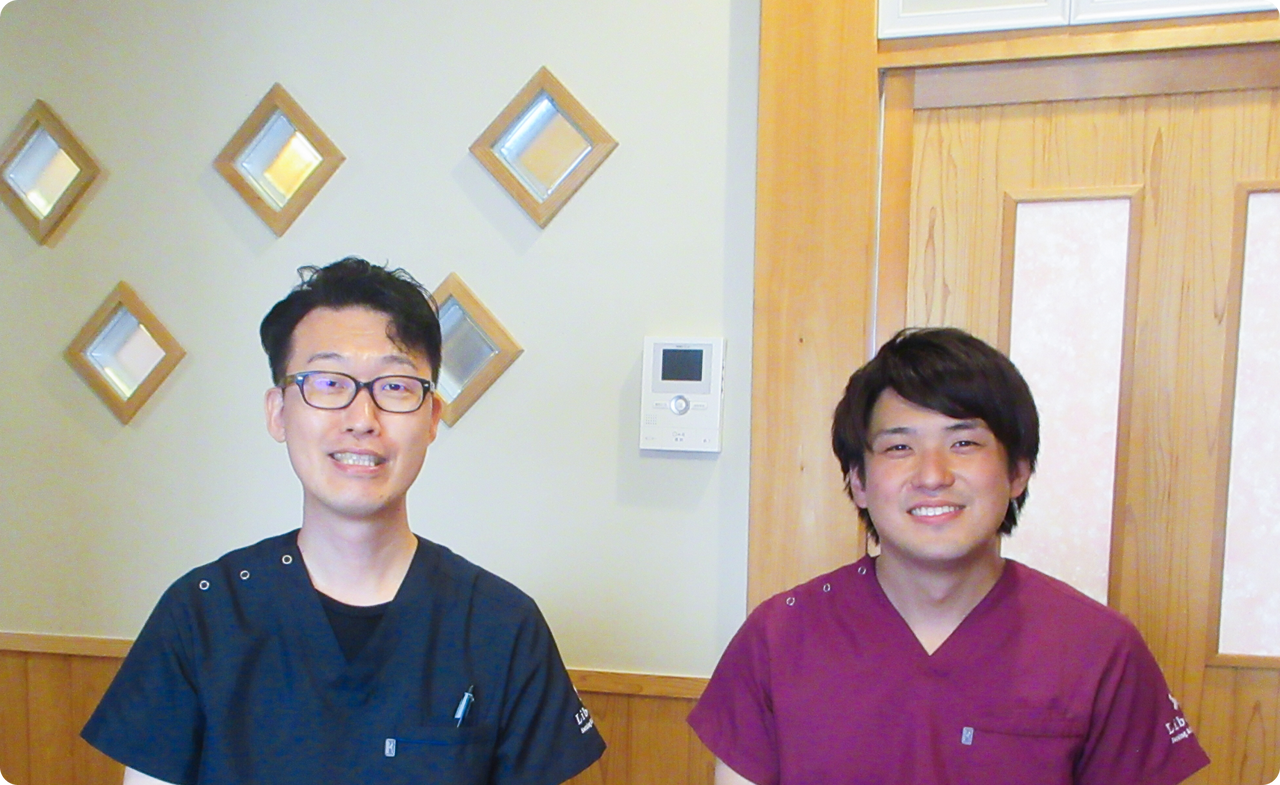
リバティ訪問看護ステーション
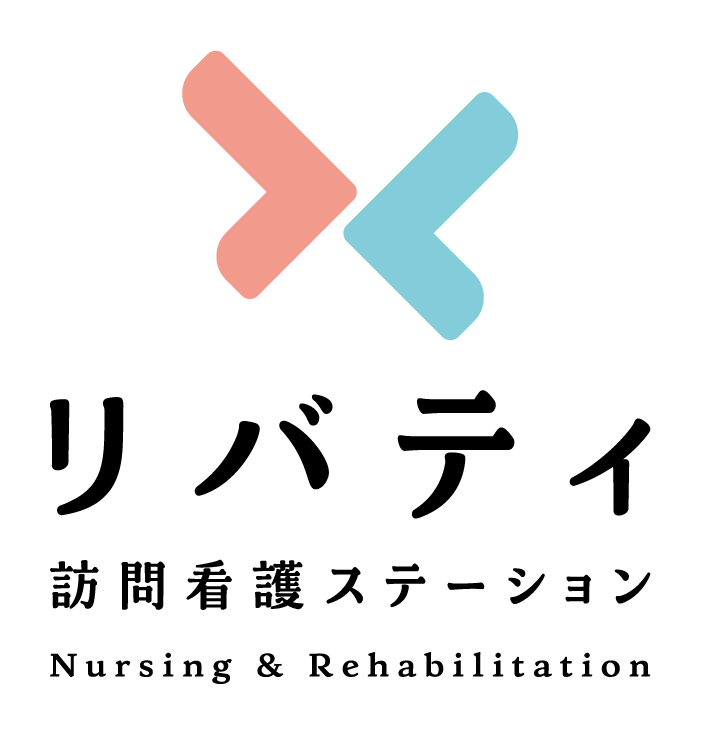
- 使用開始2024年
- 使用人数11名(2025年9月時点)
株式会社Liberty(左から)取締役山脇様・管理者西村様
株式会社Liberty様は、2024年6月にカイポケを導入いただきました。カイポケを使いながら生成AIを活用して、現場スタッフ様の業務負担の軽減に取り組まれています。主に生成AIの活用を推進している取締役の山脇様と実際に活用している管理者西村様にAI活用の経緯やAIに対する考え方、AI活用の効果などについてお伺いしました。
「幸せに働き続ける環境をつくる」ために始まった生成AIの活用
生成AIを使うことになった背景について教えてください。
(取締役)山脇様:もともと、生成AIを使いたかったわけでは全然なかったです。
前提として、看護師さんは現場をまわって利用者さんのためにケアをやりたいけれど、訪問看護の業界ってそれ以外の業務が圧倒的に多いです。書類も大事だけど、訪問も大事でバランスがなかなか難しいです。
うちの会社のミッション・ビジョンである「幸せに働き続ける環境をつくる」と「人と共に成長する企業である」というのを大事にしていますが、書類業務と訪問のバランスが難しい中、書類業務の時間を減らしていくことで、みんなが幸せに働き続けるっていうところに繋がっていくなと思っています。
スタッフ向けに現在の業務についてアンケートをとったときに、書類業務、特に計画書や報告書作成に時間がかかっていることや締め切りが迫っている短い期間で作成することがストレスになっていることがわかりました。そこから、ソフトで出来ることと現場のニーズの乖離をフィットさせるために生成AIを使うようになりました。
特に、管理者には、メンバーと向き合う時間を割いてほしいと考えています。今回は、カイポケを使っている事業所の管理者西村さんに同席してもらっています。
管理者 西村様のスタッフや組織への向き合い方について教えてください。
(管理者)西村様:訪問看護では、目の前の利用者さんに対して何ができるかを考えている方が多いです。とはいえ、一人では対応が難しいケースも多く、訪問診療さんやケアマネジャーさんなどと連携しながら解決していく必要があります。そうした中で、日々の対応に悩む場面や気持ちが重くなる瞬間も少なくありません。だからこそ、気軽に相談できる環境やコミュニケーションの壁がないなどの組織文化が大事だと思っています。
スタッフさんとの日々のコミュニケーションはどのような形でとっていますか?
(管理者)西村様:チャットが多いです。温度感だったり、文面だけなのでどう伝えるかを考えてメッセージを送っています。チャットのグループ名が「自由の広場」という名前で、会社名であるLiberty(リバティ)は「責任ある自由」という意味ですが、そこから名前を付けています。チャットでは、実際に事務所でみんなが話す感じと同じように「営業行ってきました!」「いいね!」などチャットで話しています。
(取締役)山脇様:西村さんの場合は心で通じ合って、ちゃんとスタッフを見てメッセージをしているように感じます。スタンプなどのリアクションで済ますのではなく、ありがとうってちゃんと返信しているんですよ。
(管理者)西村様:自分がやったケアを利用者さんだけに褒めてもらえるだけではなく、社内で共有することで周りからも評価してもらえる機会を作れるのもチャットのいいところのひとつなのかなと思ってます。

(管理者)西村様:この仕事は、辛いこともいっぱいありますけど、スタッフみんなが根本的に目の前の人のために何かやってあげたいと思っています。やったことで感謝を受けたり、利用者さんが目に見えて満足してくださったことに自分たち自身が満足ややりがいを感じたり、もっとこの仕事を好きになって、もっと訪問看護をやっていきたいと思える原動力になるところがあると思っています。自分はまだまだですが、スタッフさんと一緒に成長しながら伴走できたらと思っています。
熱量のある業務は人に、緊急性の低い業務はAIに
生成AIを使って最初に取り組んだことを教えてください。
(取締役)山脇様:報告書作成の効率化です。電子カルテやチャットツールから必要な利用者情報をGoogleスプレッドシートに起こしました。 ケアマネジャーさんや主治医の先生に共有する情報をこれまでの報告書の内容をもとに系統化して、生成AIにプロンプトを反映することで要約された文章を抽出することができます。
また、インパクトは小さいですが、有給などの勤怠回りの申請書類の効率化も進めています。 有給申請であれば、年次有給や特別有給などのタイトルがシートに表示されるようにGoogleスプレッドシート内で、GAS(GoogleAppsScript)を使っています。GAS内に指示する関数を入れる必要があるのですが、この関数を生成AIを活用して書き出してもらいました。これまでは、スタッフが提出した申請書類データのタイトルと申請内容が異なることがあり、修正や確認に時間がかかっていたのですが、それらの間違いがなくなりました。
最近では、訪問記録を音声のみで記録できないかテスト中です。文字起こしに時間がかかってしまうので、現時点では書いた方が早く、実運用にはなっていません。どういう時に使えそうかを考えると、初回訪問では先生からの指示や病院からのサマリーなど情報が多いので、PDFで出力したものをベースに、生成AIで作成できるとよさそうだなと考え、試行錯誤中です。
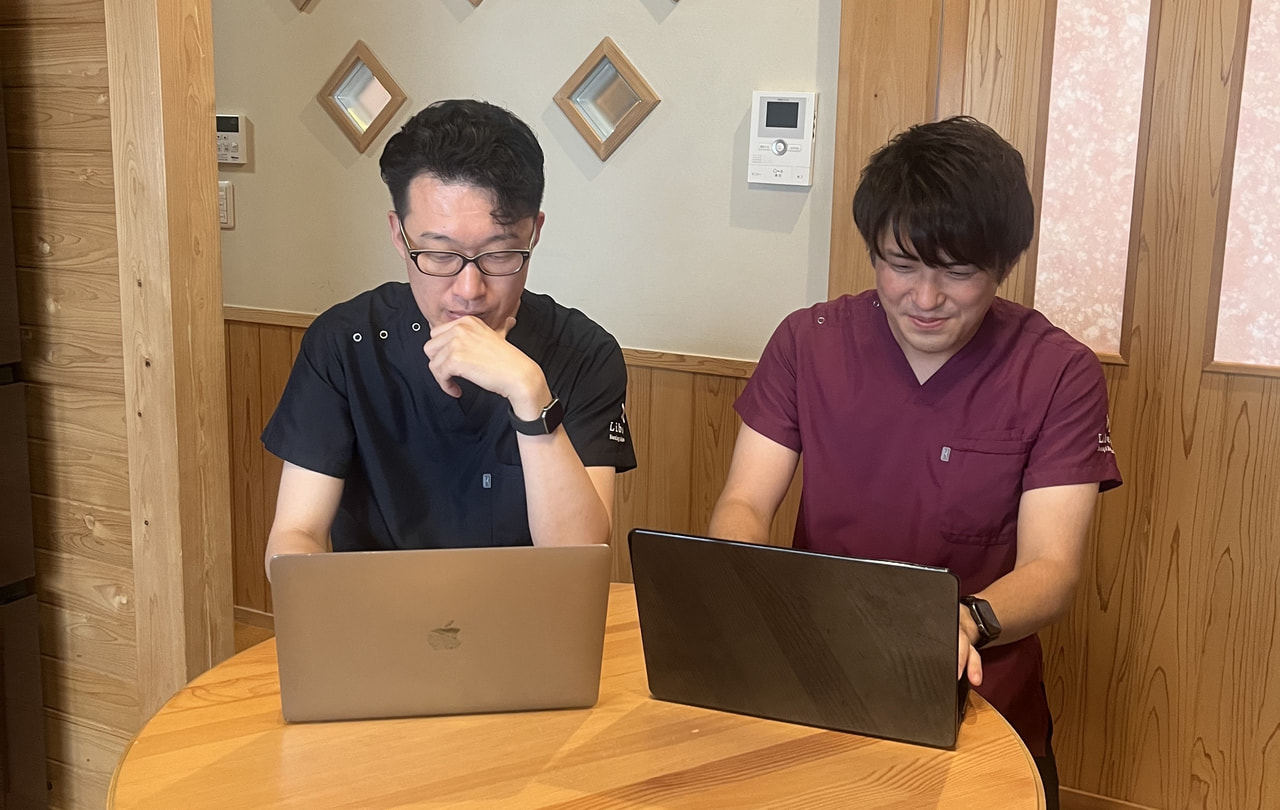
生成AIを使うようになって変化はありましたか?
(取締役)山脇様:現場として変わったと思える肌感覚は、いまはそこまでは強くないのではないかと予測しています。「実感」になるには、色んな業務に無意識にAIが溶け込んでいて、1件の訪問、1日、1週間、1ヶ月の中での業務が短くなったときに「業務の負担が軽くなっているぞ」と初めて実感がわくのではないかと思います。まだまだ先は長いということです。(笑)
(管理者)西村様:
まだまだAIを使いこなせていないのが正直なところなのですが、私の感覚でいうと、情報の取捨選択や優先順位のつけ方の判断がしやすくなりました。
例えば、報告書であれば急いで伝える必要のないことは生成AIにやってもらって、今すぐ伝えないといけない情報は電話で伝えるなど、情報にも優先順位があって、その判断がしやすくなったと思います。
(取締役)山脇様:個人的には、生成AIはバックオフィス機能だと思っています。リバティの中で現場は最前線で、スタッフさんは一番大事な人たちです。みんなすごく真面目なので、全部の業務を100%の熱量でやっていると疲弊してしまう・・・だから、現場への熱量を集中させることが大事だなと思っていて。
熱量の方向性を経営側が決めることで、現場以外の時間を減らしていくことで現場にグっと熱量が向くようになっていると自分は思います。
実際に、生成AIに対してスタッフの反応はどうでしたか?
(取締役)山脇様:はじめは「ログイン方法がわからない」という反応が多かったです。
だから、スタッフみんなの業務の導線を考えて、使えるように運用を落とし込みました。こちら側から「はいこれやって」と渡すと、やらされた感が強かったり、どう使えばいいか分からないので使えない、という反応になってしまうので、どのくらいかみ砕けばスタッフさんに使ってもらえるのか、スタッフさんの反応を見ながら試行錯誤して、徐々に使ってもらう範囲を広げていきました。
私もとても分かるのですが、使い方が分からないものを使うことは、便利よりもストレスがかかりますから。
まずは触ってみる。面白そうと思ったらすぐダウンロードする。
これから生成AIを活用していきたいという方に伝えたいこと
(取締役)山脇様:まずは触ってみることです。使ってみて、まったく自分の思うようにならないのは全然失敗ではないです。そこから、なぜ思うようにいかないのか、そもそもやりたかったことは何だったか?本当はどういうフィードバックが欲しかったのか?のような問いを考えるのが大事だと自分は思います。
ここで躓く方も多いかもしれませんが、安心してください。そのまま、そのAIに聞くのがおすすめです!「自分はこう思ってたけど、違う回答が返ってきたのはなぜ?」と。そしたら、見事な分析が返ってくるはずです。
もうひとつAIがよりこちらの意図に近い完成度の回答をしてくれるようになるとっておきの方法があります。それは「AIに逆質問させること」です。例えば「君(AI)の理解を深めるために、必要なことを私にいくつか質問してください」と入力すると「これはどういう意味ですか?」「あなたの思いはなんですか?」など聞いてきます。その質問にこちらが答えていくと、完成度の高い回答に近づいていくというワケです。
お気づきの方がいらっしゃるかもしれません。
そう、こちらの指示の”量”と”詳細”が圧倒的に足りないということに。
これは、人間関係にもそのまま直結すると思っていて、AIへの指示は具体的でないと思い通りに返ってこないことが多いです。思い通りの「思い」は何なのかを言語化できないと、やりたいことはできないと思います。だからAIで、言語化力を一緒に磨いていくことで人間関係の練習にもなると個人的には思っています。
AIのいいところはいつでもどこでも使えて、疲れないし休まないところです。 こっちが疲れるまでは(笑)いつでも相手してくれるのでまずは触ってみて、触り続けてみるといいと思います。
人間がやらないといけない業務以外のものをゼロにする
今後、特に力を入れていきたいことは何ですか?
壮大な目標かもしれませんが、人間がやらないといけない業務以外のものをゼロにしたいです。 そのためには、ひとつのAIソフトに頼らないことが鍵なのかなと思います。 いろいろ組み合わせていき、自分たちに合っているものを自分たち好みに使っていく必要があると思います。
最後に、本末転倒な話かもしれませんが、AIに固執するのもよくないと思っています。 「幸せに働き続ける環境」のための業務改善が目的なら、何をAIに任せるのか、業務のどの部分を人とAIをMIXにするのか?AIには頼らず人が担うべきものなのか?色々試行錯誤して、スタッフみんなの反応をみながら、ゆるやかに、まろやかに進めていくといいのかなと思います。 AIを使うことが目的にならにように、自分も気をつけたいです。

